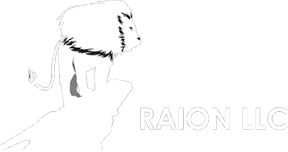その情報、本当に正しい?災害時に注意したい“デマ”の拡散
地震、台風、大雨など、自然災害が発生したとき。
私たちがすぐに頼るのが、SNSやチャットアプリでの情報収集です。
でもその便利さの裏で、気をつけたいのが“災害デマ”。
「○○ダムが決壊」「○○駅で火災」など、事実と異なる情報が拡散されることで、パニックを招いたり、救助活動の妨げになったりするケースも。

なぜデマが広がるのか?
実は、デマを最初に広めようとするのは、必ずしも“悪意のある人”ばかりではありません。
・「善意のシェア」がかえって被害を拡大することも
・情報の出どころが不明瞭なまま、RTや拡散が繰り返される
・AI生成画像やフェイク動画が、リアルに見えることで信じてしまう
「自分だけは大丈夫」と思っていても、非常時は判断力が鈍るもの。
冷静な対処が難しいからこそ、平時から“情報リテラシー”を高めておくことが重要です。
実際にあった「災害デマ」の事例
2016年 熊本地震
「動物園からライオンが逃げた」→拡散され、警察が出動する騒ぎに
2018年 西日本豪雨
「コンビニが無料開放している」→誤情報の拡散で混乱
2021年 東日本大震災10周年
偽の追悼イベント情報が出回る
どれも一見“ありそう”な内容だからこそ、多くの人が信じてしまったケースです。
デマに振り回されないために。今できる3つの対策
情報源を必ず確認する
公的機関(気象庁、自治体、報道機関など)の発信かどうかをチェック。
共有前にワンクッション置く
「これ、本当かな?」と思えたら、それだけでブレーキになります。
フェイク画像・動画に注意する
被災地以外の映像や過去の災害映像が、あたかも“今の被害”のように投稿されていることも。
「誰が」「いつ」「どこで」撮ったものか、出典を確認しましょう。
情報も、命を守るツールになる
デマは、時に“もうひとつの災害”になりかねません。
正確な情報を受け取り、必要に応じて人に届ける力は、災害時にこそ求められます。
普段から、
・正しい情報源(NHK、防災アプリなど)をブックマーク
・SNSのリテラシーを高める
・家族や職場とも「情報確認のルール」を共有
といった備えをしておくことで、“いざ”というときに冷静に動けるはずです。
【今日のサクッとチェック!】
SNSの投稿をシェアする前に「発信元」「日付」「信ぴょう性」をチェックしよう!
本記事に登場する会社名、商品名、その他サービス名は各社の商標または登録商標です。