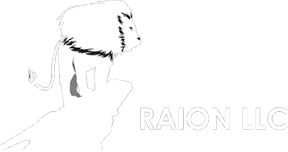Google検索の「AIモード」で何が変わる?検索体験の次のステージ
「いつもは“キーワード”だけで検索してるけど、AIモードって結局何ができるの?」
そんな疑問を持っている人、多いはず。
2025年9月、Googleは検索機能に「AIモード」(AI Mode)を正式に導入し、日本語でも使えるようになりました。
従来の検索とは何が違って、僕たちの検索習慣にどんな影響があるのか。
“使える”ポイントを中心に解説します。

AIモードってどういうもの?
AIモードとは、Google検索で「従来のリンクリスト」型ではなく、生成AI(Googleの Gemini モデルベース)を使って質問に対する「要約的な回答」を直接取得できるモードのこと。
複雑な問いや長めの質問、複数の情報要素を含むテーマでも、AIがサブトピックに分解して最適な情報を集約・整理してくれます。
特徴を整理すると、
・質問を文章で投げかけることが可能(対話形式でフォローアップもできる)
・ウェブ上の多数の情報源を同時に参照 → 質問をサブトピックに分けて回答をまとめる「Query Fan‑Out」技術を採用
・回答にはウェブリンクも添えられるので、「裏付け」をチェックしやすい
・テキスト入力に加えて、音声入力・画像を使った問い合わせなどマルチモーダルな操作も対応中/対応予定
日本語対応後に注意したい“良さ”と“限界”
良いところ
・質問や疑問があれば「文章でそのまま聞ける」ので、キーワードを選ぶストレスが減る
・複数サイトを自分で開いて探す手間が省ける → 時間が短縮できる
・情報を整理してくれるので、特にリサーチや学習、旅行・計画立案など複雑なタスクに強い
注意・限界
・AIが生成した回答には誤りが含まれることがあり、「裏取り」が必要
・新情報・リアルタイムデータが必ず反映されるわけではない
・従来のサイトへのトラフィックが減るかもしれず、情報発信側のSEO影響などが議論中
仕事・学び・生活でどう使いこなす?
AIモードを日常に活かすための“ポイント”を3つ挙げます。
質の良い質問を意識する
単に「人気店」だけでなく、「予算・ジャンル・アクセス条件」などを含めると、AIモードはより使いやすくなります。
フォローアップ質問を活用
初回の要約を見て「もっと具体的な事例がほしい」などと質問を追加することで、より自分に合った情報が得られます。
信用できるソースをチェックする癖をつける
AI回答に出てくるリンク先や参照元を確認する/複数の情報源を比較する、という習慣が大事です。
検索の主導権が“より自分の手に”渡る時代
AIモードの登場は、検索のあり方における一つの転換点。
「検索=キーワードを考えてサイトを探す」のではなく、「疑問をそのままAIに聞いて、整理された答えを得る」ことが当たり前になってくるでしょう。
ただし、便利だからといって使いっぱなしではなく、情報の裏付け・精度の見極めを意識すれば、検索力はぐっと強くなります。
【今日のサクッとチェック!】
今の疑問を一つ、AIモードで検索してみよう!
本記事に登場する会社名、商品名、その他サービス名は各社の商標または登録商標です。