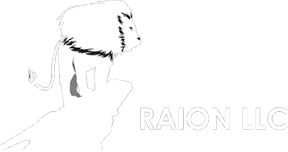“スマホ脳”から脱却せよ!集中力を取り戻すアナログ習慣
「ちょっとだけSNSをチェックするつもりが、気づけば30分…」
そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか?
現代人は1日に平均4〜5時間もスマートフォンを見ているとされ、“スマホ脳”と呼ばれる集中力の低下や記憶力の悪化が問題視されています。
とくに20〜30代の若手ビジネスパーソンの中には、「スマホが手元にあるだけで集中できない」「隙間時間がすべてスマホに吸い取られる」といった悩みを抱える人も少なくありません。

スマホ脳とは?デジタル依存の実態
「スマホ脳」という言葉は、スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセン氏の著書『スマホ脳』から広まりました。
スマートフォンの通知やスクロール行為は、脳の報酬系を刺激し、一種の“依存症状態”を生み出すのです。
その結果、以下のような影響が現れることが指摘されています。
・集中力の低下
・記憶力の低下
・睡眠の質の悪化
・情報の浅い理解
・常に「急かされている」ような感覚
こうした状態は、仕事の生産性や人間関係にもじわじわと悪影響を及ぼします。
スマホ脳から脱却するアナログ習慣
では、どうすれば“スマホ脳”から抜け出せるのでしょうか?
その鍵は、「あえてアナログに戻す」ことです。
紙のノートにメモする
会議や勉強はデジタルではなく、あえて「紙のノート」でメモを取りましょう。
手を動かして書くことで、脳への定着率が高まり、集中力も上がります。
“スマホの代わり”を用意する
・目覚まし時計を使う
・本は紙で読む
・音楽はスマートスピーカーで流す
など、“スマホでなくてもいいこと”を切り離すと、スマホ依存を少しずつ緩和できます。
スマホの物理的距離を取る
・勉強や作業中は別の部屋に置く
・SNSやニュースアプリをログアウトしておく
・通知をオフにする
物理的・心理的な距離を作ることで、無意識のチェック癖が減ります。
デジタルとアナログ、うまく使い分けよう
スマホ自体が悪いわけではありません。
大切なのは、“必要なときだけ使う”という自律的な関わり方です。
デジタルとアナログのバランスを見直すことで、集中力・記憶力・自己管理力が向上し、より深く、豊かな時間を過ごすことができるはずです。
【今日のサクッとチェック!】
紙のノート、目覚まし時計、物理的距離でアナログに切り替えてみよう!
本記事に登場する会社名、商品名、その他サービス名は各社の商標または登録商標です。