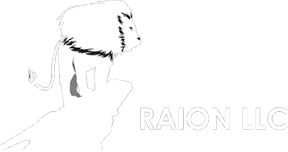GPTとは何か? ― テキストを“理解し、生成する”AIの仕組み
いまやニュースやSNSで頻繁に見かける「ChatGPT」。
その名前にある「GPT」とは、Generative Pre-trained Transformer(生成型事前学習トランスフォーマー)の略称です。
この技術こそが、文章を理解し、新しいテキストを生成するAIの中核を担っています。
ここでは、GPTの仕組みと進化、そして何が「すごい」のかを技術的に解説します。

GPTの基本構造:Transformerとは何か
GPTの根幹にあるのが、Transformer(トランスフォーマー)という自然言語処理モデルの構造です。
これは2017年にGoogleが発表した論文「Attention Is All You Need」で提案され、以降のAI言語モデルの標準構造となりました。
Transformerの特徴は、「自己注意機構(Self-Attention)」にあります。
従来のRNNやLSTMのようにテキストを順番に処理するのではなく、文全体を一度に見渡し、単語同士の関係性(文脈)を学習するのです。
たとえば「私は銀行で口座を開いた」という文があった場合、「銀行」という単語が「金融機関」であることを文脈的に理解できます。
一方で「river bank」という文が出れば、同じ“bank”でも“土手”を意味することを判断できる。
この“文脈理解”を可能にしたのが、Transformerの革新です。
GPTの「事前学習」と「微調整」
GPTは名前の通り、「Pre-trained(事前学習)」されたモデルです。
これは、インターネット上の大量の文章データを使って学習し、言語のパターンや知識を統計的に把握しているということを意味します。
たとえば「東京は日本の〜」と入力すると、高確率で「首都」という単語を生成できる。
これはGPTが“意味を知っている”のではなく、「その単語が次に出現する確率が高い」ことを統計的に予測しているのです。
さらに、OpenAIはこの事前学習モデルに対して「指示に従うように調整(Instruction Tuning)」や「人間の好みに合わせた最適化(RLHF:人間のフィードバックによる強化学習)」を行っています。
これにより、ChatGPTのように自然な対話や文書作成が可能な応答AIが実現しました。
GPTはどう“考えている”のか?
GPTは人間のように思考しているわけではありません。
内部では確率計算によって、次に続く単語の出現確率を予測しています。
しかし、その確率予測が極めて精密で、膨大な文脈情報を保持しているため、まるで“理解しているように見える”のです。
言い換えれば、GPTは「統計的予測による擬似的理解エンジン」。
文法、語彙、論理展開、会話の流れなどを確率モデルとして再現しているといえます。
GPTの応用領域
GPTは単なるチャットボットではなく、すでに多様な領域に応用されています。
・自然言語処理(NLP):要約、翻訳、感情分析、文書分類
・ソフトウェア開発支援:コード自動生成、リファクタリング支援
・教育・研修分野:個別学習サポート、教材自動生成
・ビジネス支援:メール作成、レポート生成、顧客対応の自動化
また、GPT-4以降ではマルチモーダル(画像+テキスト)対応も進み、ビジネス領域での「知的作業の自動化」が急速に進んでいます。
限界と課題:正確さと“幻覚(ハルシネーション)”問題
GPTは万能ではありません。
とくに課題となるのが、「ハルシネーション」と呼ばれる誤情報生成です。
自信をもって間違った回答をするケースがあり、これは統計的予測モデルである以上、避けられない性質でもあります。
そのため、GPTを実務で使う際は、「人の最終確認」+「信頼できるソースの併用」が不可欠です。
また、データのバイアス(偏り)や著作権の問題も、今後の技術発展とともに議論が続いています。
【今日のサクッとチェック!】
大量データによる事前学習+人間のフィードバック調整で高精度応答が可能に!
本記事に登場する会社名、商品名、その他サービス名は各社の商標または登録商標です。